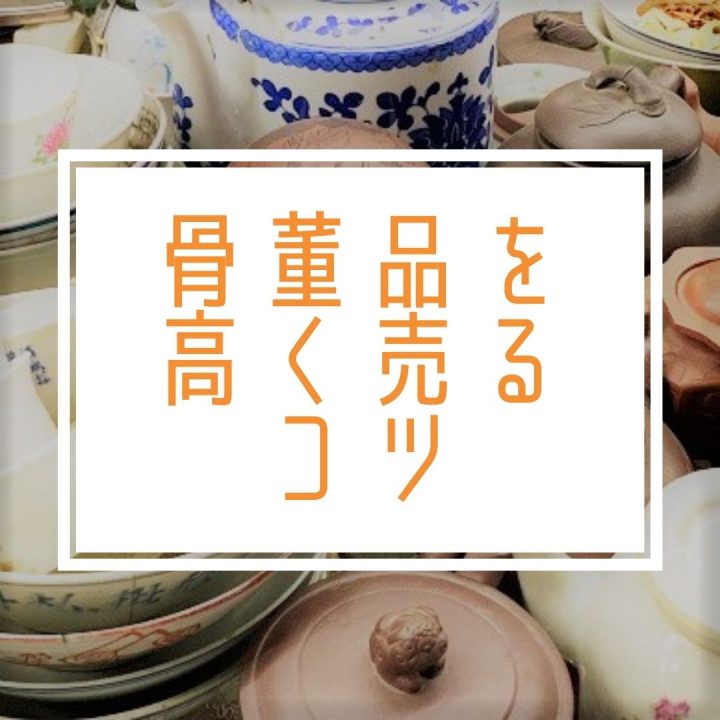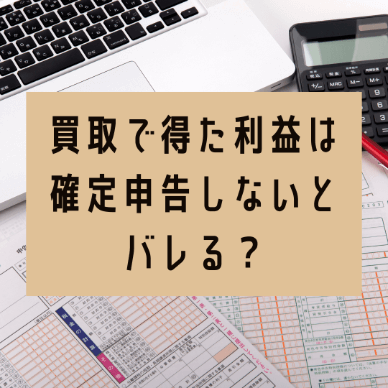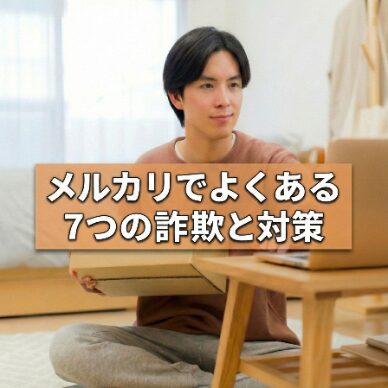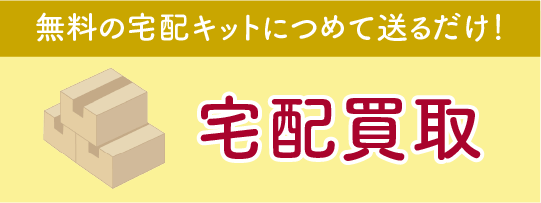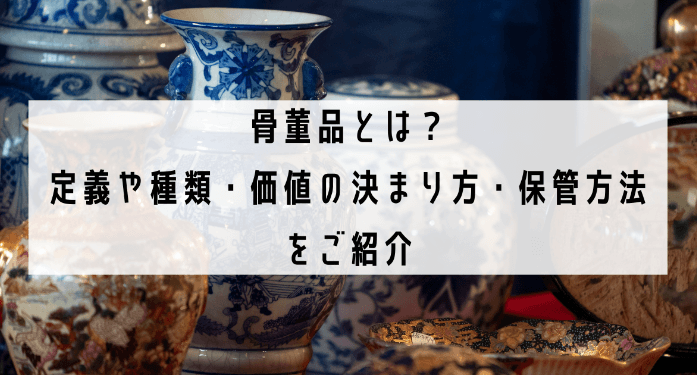
相続や遺品整理の際に、工芸品・美術品を手にすることがあるかと思います。ただ、それが骨董品にあたるのか、価値のあるものなのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容について徹底解説していきます。
- 骨董品とはなにか
- どのような種類があるのか
- 価値はどう決まるのか
また骨董品を高く売るコツも紹介しますので、売却を考えている人は合わせてご確認ください。
ぜひ最後まで目を通していただき、骨董品の理解を深めましょう。
【目次】
1.骨董品の定義とは?

骨董品とは、一般的に作られてから100年以上が経過した、希少価値のある工芸品や美術品の総称です。この「100年以上」という基準は、1934年にアメリカで定められた通商関税法がもとになっていますが、法律上の明確な定義ではありません。
現在では、製造から100年未満であっても、歴史的な価値や希少性が認められるものは「アンティーク」や骨董品として扱われる場合も多くあります。たとえば、古い時代の伊万里焼の皿や、江戸時代の武具、明治時代のガラス製品などがこれにあたります。
単に古いだけでなく、その時代を映し出す背景や、作りの美しさに価値が見いだされるのが骨董品なのです。
1-1.骨董品と古美術品は何が違う?
骨董品と古美術品は、現在ではほとんど同じ意味の言葉として使われていますが、厳密には少しニュアンスが異なります。
本来、「古美術品」は骨董品の中でもとくに芸術性や鑑賞価値が高い絵画や彫刻、茶道具などを指す言葉です。一方「骨董品」は、古美術品に加えて、昔の人々が日常で使っていた食器や家具、おもちゃなど、より幅広い品物を含む言葉として使われてきました。
たとえば、江戸時代の有名な絵師が描いた掛軸は「古美術品」といえますが、同時に骨董品でもあります。そのため、両者に明確な線引きはありませんが、古美術品は骨董品という大きなカテゴリの中に含まれる、より美術的価値の高いもの、と理解すると分かりやすいです。
2.骨董品の種類
骨董品は下記のようにいくつか種類があります。
- 絵画・掛け軸
- 茶道具
- 焼き物・陶磁器
- 刀剣・甲冑類
- 象牙・珊瑚・翡翠製品
それぞれどのような工芸品・美術品を指すのか、順に解説いたします。
2-1.絵画・掛け軸
絵画や掛け軸は「古美術品」と呼ばれ、骨董品の1種です。
絵画は、西洋で描かれた「西洋画」と日本の「日本画」で大きく分類され、さらに素材や技法で分類されます。掛け軸は「書」「絵」「書と絵を合わせた作品」の3つに分類されます。
作品の種類としては、「書」であれば漢詩や和歌など、「絵」であれば水墨画や肉筆浮世絵などとさまざまです。
いずれも、作者や種類によって価値は異なるため、詳細は鑑定書や付属品を確認するようにしましょう。
2-2.茶道具
茶道具とはお茶の道具のことです。また茶器だけではなく、水差しや柄杓、茶棚など茶道に関するさまざまなものが対象になります。
茶道具の骨董品としての価値はピンからキリまであり、希少性の高い品であれば数千万円の値段がつくこともあります。
2-3.焼き物・陶磁器
焼き物も骨董品に属し、今回はその中の「陶磁器」を紹介いたします。陶磁器は「陶器」と「磁器」をまとめて総称する言葉です。
「陶器」と「磁器」のいちばんの違いは素材で、陶器は土が主な素材であるのに対し、磁器は石物が主な素材として制作されています。
陶磁器は産地によって種類が分けられ、「瀬戸焼」「常滑焼」「有田焼」など多くの種類があります。
2-4.刀剣・甲冑類
刀剣・甲冑類も骨董品の一種です。
刀剣は、「刀」「太刀」「槍」などの刀剣自体の種類や、「古刀」「新刀」など制作された時代によって、さらに細かく分類されます。甲冑類は、「胴体部を保護する鎧」と「頭部を保護する兜」からなる防具のことを指します。
主に下記4つの種類に分類され、時代ごとの主要戦法から作られ方が異なっている形です。
- 短甲・挂甲…古墳時代から使用された甲冑
- 大鎧…平安・鎌倉時代に誕生した甲冑
- 胴丸・腹巻・腹当…鎌倉時代以降に誕生した甲冑
- 当世具足…戦国時代末期に種類となった戦法に適した甲冑
また、刀剣類については所持するために「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
相続時や譲渡時に、登録証も合わせて確認をおこないましょう。
2-5.象牙・珊瑚・翡翠製品
象牙(ぞうげ)、珊瑚(さんご)、翡翠(ひすい)を用いて作られた作品は、骨董品に属します。
下記のような作品で使用されており、価値はさまざまです。
- 彫刻品
- アクセサリー
- 置物
- 実用品
またそれぞれ細かく種類が分けられていて、その種類によっても価値が変わってきます。
たとえば、珊瑚であれば「赤珊瑚」「桃珊瑚」「白珊瑚」の色で分類され、その色の違いや珊瑚の種類で価値が決まります。象牙・珊瑚・翡翠製品の骨董品を所持している場合は、さらに細かい種類を確認するようにしましょう。
次章では、骨董品の種類以外の価値が決まる要素についてご紹介します。
3.骨董品の価値を決める6つの要素

実際に骨董品の売却をおこなう際に、買取価格はどのように決まるのか気になる方が多いかと思います。
骨董品の価値は主に6つのポイントで決まります。
- 希少価値があるかどうか
- どのような歴史的背景を持っているか
- 優れた作品であるかどうか
- 作品や作者の知名度
- 制作された年代はいつか
- 保存状態
順に解説していきます。
3-1.希少価値があるかどうか
現存する数が少なく希少性が高い品であれば、価値が高まります。
人気のある品であっても、世の中で多数出回っている品であれば価値が下がるので、市場も合わせて確認が必要です。
3-2.どのような歴史的背景を持っているか
3-3.優れた作品であるかどうか
作品が「美しい」「上手い」「美術的な評価が高い」とされれば、価値が高まります。
ただ他のポイントに比べ抽象度が高く、国や地域の文化の違いによっても評価の基準が異なるため、何をもって「優れている」と判断するかは不明確です。
そのため、価値を把握したい場合は、一度専門家に鑑定を依頼するのが良いでしょう。
3-4.作品や作者の知名度
作品や作者の知名度は価値に直結します。有名な作家によって作られた作品、世の中で話題になっている作品であれば価値が高まります。
もちろん、贋作の場合は価値が下がるので、注意して確認するようにしましょう。
3-5.制作された年代はいつか
骨董品が制作された年代が古ければ古いほど、価値があがりやすいです。同じ様な骨董品であっても、江戸時代と昭和時代のもので比べると江戸時代のもののほうが現存数が少ない可能性が高いためです。
ただ、骨董品の種類によって作られ始めた時期や流通量が異なるため、年代が古ければ必ずしも価値が高いとは言いきれません。
そのため、前述した「希少価値があるかどうか」と合わせて確認するようにしましょう。
3-6.保存状態はいいか
骨董品の保存状態が良好であればあるほど、価値が高まります。小さなキズがあるだけでも価値が下がる可能性があるため、適切な場所で丁寧に保管するようにしましょう。
骨董品は繊細なため、お手入れも下記をポイントに丁寧におこなうことが大切です。
- 骨董品を触れる際は、専用の布製手袋を着用する
- 直射日光のない室内で、湿気の少ない天気の良い日に行う
- お手入れ方法に不安を感じる際は、無理に行うのではなく最低限の対応にする
保存管理・お手入れに悩む場合は、専門業者に相談するのも1つの手段です。
4.骨董品の劣化を防ぐ保管方法
ここからは、骨董品の劣化を防ぐ保管方法について解説していきます。
4-1.骨董品の正しい保管方法
骨董品を保管する際は、以下の3点に気をつけるのが基本です。
- 湿度は40%〜60%にする
- 温度は15度〜25度にする
- 直射日光は避ける
一つずつ解説します。
4-1-1.湿度は40%〜60%にする
骨董品を保管する際の湿度は、年間を通して40%〜60%の範囲に保つのが理想です。
湿度が60%を超えるとカビが発生しやすくなり、とくに木製品や紙、繊維製品に深刻なダメージを与えます。逆に湿度が40%を下回るような極端な乾燥は、木製品の割れや漆の剥がれなどを引き起こす原因です。
たとえば梅雨の時期は除湿機を、冬の乾燥する時期は加湿器を上手に使い、温湿度計で常に数値をチェックする習慣をつけましょう。
4-1-2.温度は15度〜25度にする
骨董品の保管に適した温度は、急激な変化が少ない15度〜25度の範囲が目安となります。
高すぎる温度は、素材の化学的な劣化を早める原因になってしまいます。また、温度の急な変動は、素材の膨張と収縮を繰り返し、ひび割れや歪みを引き起こす場合があります。
私たちが快適だと感じる室温が、必ずしも骨董品にとって良いとは限りません。一年を通して安定した温度を保てる、押し入れの天袋や納戸などが保管場所として適しています。
4-1-3.直射日光は避ける
骨董品は、直射日光や強い照明の光が当たらない場所に保管するのが鉄則です。紫外線は、有機物の分子を破壊する強いエネルギーを持っており、着物や絵画などの色褪せ、紙や木の劣化を急激に進行させるからです。
窓際に置くのはもちろん、室内の蛍光灯の光でも長期間当たり続けると影響が出ます。保管する際は、箱や引き出しにしまうか、布を掛けるなどの対策をおこないましょう。
4-2.骨董品の素材ごとに気をつけたい保管ポイント
骨董品の素材ごとにも、気をつけたいポイントがあります。ここでは、以下5つの素材に分けて保管のポイントを解説していきます。
- 陶磁器
- 木製品
- 金属製品
- 書画・紙製品
- 繊維製品
それぞれ解説していきます。
4-2-1.陶磁器の保管ポイント
陶磁器は、衝撃による破損と、金彩や絵付けの剥落が弱点です。そのため一つずつ薄紙で包み、箱に保管しましょう。重ねる際は器の間に当て紙を挟むのが必須です。
急激な温度変化もひび割れの原因になるため、直射日光や暖房の近くは避けてください。
4-2-2.木製品(漆器など)の保管ポイント
木製品の場合、極端な乾燥や湿気、紫外線が最大の敵です。反りやひび割れ、カビを防ぐため、直射日光やエアコンの風が直接当たらない、温度変化の少ない場所に保管しましょう。
普段の手入れは、柔らかい布での優しい乾拭きが基本です。
4-2-3.金属製品(鉄・銀など)の保管ポイント
金属製品では、湿気や皮脂による錆・変色を防ぐことが最も重要です。素手で触らず、布手袋を使いましょう。空気に触れないよう布で包み、桐箱やチャック付き袋で保管するのが理想です。
銀製品は変色の原因となるゴム製品と一緒に置かないでください。
4-2-4.書画・紙製品(掛軸など)の保管ポイント
書画・紙製品は、湿気・虫・光によってシミや虫食い、色あせが起こります。そのため、調湿・防虫効果のある桐箱での保管が最も理想的です。
直射日光や蛍光灯を避け、年に数回は湿気の少ない晴れた日に虫干しをおこない、状態を確認することが大切です。
4-2-5.繊維製品(着物など)の保管ポイント
繊維製品は、湿気によるカビ、虫食い、光による色あせを防ぎましょう。保管は調湿効果のある桐たんすが最適です。「たとう紙」に包み、防虫剤は着物に直接触れないように置きます。
また年に数回、晴れて乾燥した日に虫干しをおこなうと長持ちします。
5.骨董品を高く売るコツ
ここまでは、骨董品の意味や種類、価値が決まる要素について解説してきました。本章では、骨董品の売却を考えている方向けに「高く売るコツ」をお伝えします。
骨董品を高く売るコツは、主に以下の6点です。
- 骨董品の価値を把握する
- 査定理由を把握する
- 鑑定書などの付属品を揃えておく
- 丁寧に保存をしておく
- 時期を見極める
- 迷ったらまずは査定を
骨董品は、買取時期や管理方法などさまざまな要因によって、買取価格が変動します。
そのためまずは「査定」をおこない骨董品の価値を把握したうえで、丁寧な保管、適切な時期に売却をおこなうようにしましょう。
「骨董品を高く売るコツ」については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
6.【まとめ】骨董品の定義や価値を理解し、適切な保管や買取を
いかがでしょうか。この記事では、「骨董品の定義・種類」「価値の決まり方・高く売るコツ」をご紹介いたしました。
ただ、一般の方が実際に細かい価値まで見極めるのは難しいかと思います。そのため、骨董品をお持ちの方はまずは鑑定や査定に出してみることをおすすめします。
玉光堂では、骨董品の高価買取を実施中です。骨董品の売却を検討している方は、ぜひ玉光堂の高価買取をご利用ください。
玉光堂の選べる買取方法