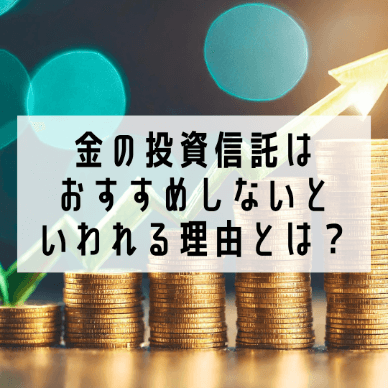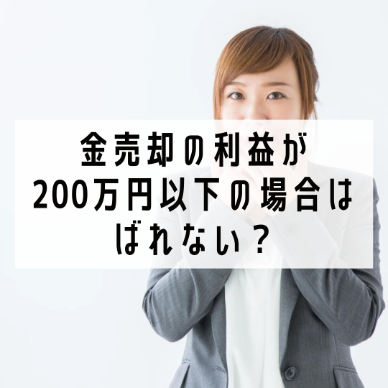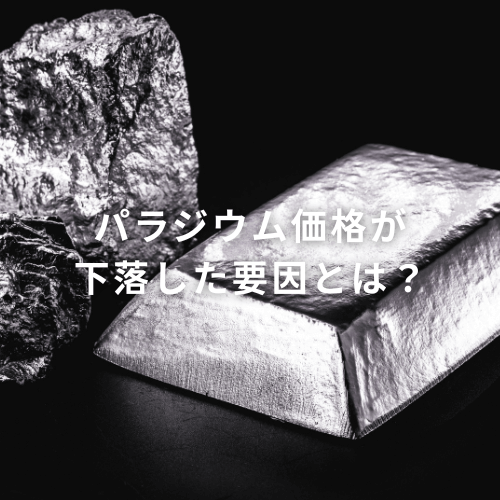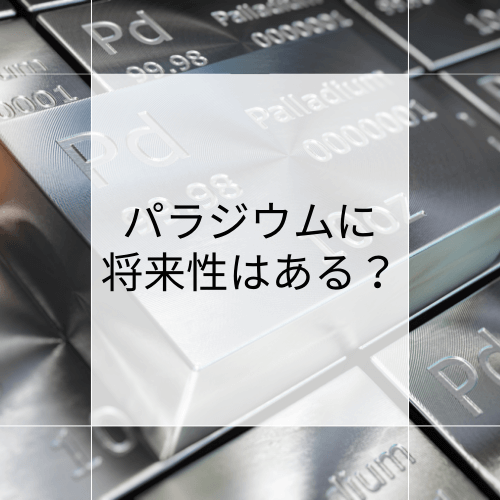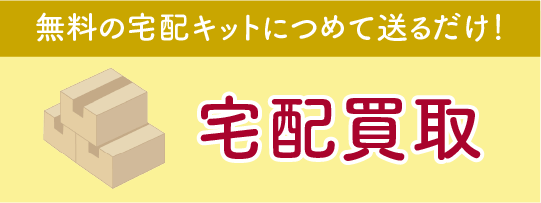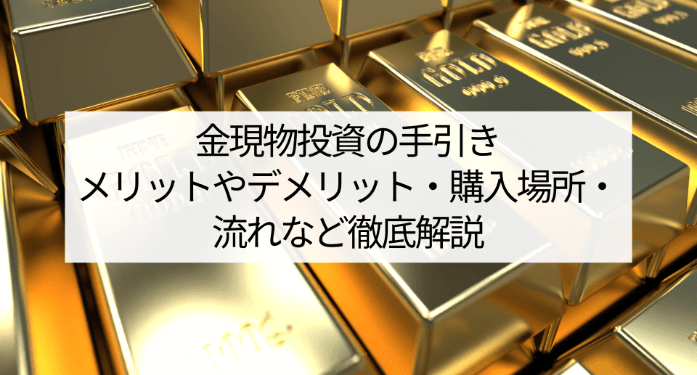
株式や投資信託のような資産とは異なり、それ自体が価値を持つ「金現物(インゴットや金貨)」は、最強の安全資産として注目されています。
しかし、いざ現物を買おうと思っても、「どこで買えるの?」「手数料は?」「買った金はどこに保管すれば安全?」といった具体的な疑問や不安も多いでしょう。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- この記事で解説していること
- 金現物投資の基本からメリット・デメリット
- ほかの金投資方法との比較
- 投資できる金現物の種類と特徴
- 金現物の購入場所
- 金現物購入の流れと手数料
- 購入した金現物の保管方法
- 金現物投資にかかる税金
金の現物投資について網羅的な内容を解説しているため、金現物投資を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。
金相場1g円の過去最高水準!
今が売り時です!
他店に負けない金の高価買取を実施中
金の買取なら、「玉光堂」の高価買取の「玉光堂」まで。
【目次】
1.金現物への投資とは?

金現物への投資とは、インゴットや金貨といった「モノとしての金」を、自分自身で直接購入して所有する投資手法です。株式や投資信託のような金融商品と違い、実物そのものが資産となります。
金現物投資の主な目的は、金の価格が上昇したタイミングで売却し、購入時との差額を利益として得ることです。また、実物を手元に置けるという物理的な所有の満足感や、万が一の経済危機への備えとして選ぶ人も多くいます。
1-1.金現物に投資するメリット
金現物に投資する最大の強みは、発行元が存在しないため「信用リスク」がない点です。信用リスクとは、たとえば株式であれば発行元の会社が倒産すると、その株式の価値がゼロになってしまう危険性を指します。
金は「モノ」そのものに価値があり、特定の国や企業の業績に左右されません。そのため、世界中のどこでも価値が認められます。
とくに物価が上がるインフレの際、お金の価値が下がっても金の価値は下がりにくい傾向があり、資産を守る力に優れています。
1-2.金現物に投資するデメリット
金現物に投資するデメリットは、保有していても利息や配当金を一切生み出さない点です。銀行預金や株式保有と異なり、持っているだけでは資産は増えません。金の現物投資で利益を得るためには、購入した価格よりも高い価格で売却することが必須です。
また、実物として所有するため、盗難や紛失の危険が常につきまといます。これを防ぐためには、自宅に高性能な金庫を設置したり、銀行の貸金庫を契約したりする必要があり、管理するためのコスト(費用)が発生します。
2.【金投資方法の比較】現物・純金積立・ETF(投資信託)の違い
金投資の方法は、大きく「現物投資」「純金積立」「ETF(投資信託)」の3種類に分けられます。以下の表では、それぞれの特徴を比較しました。
| 投資方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 金現物投資 | 実際に「モノ」として金を所有する | 実物ならではの絶対的な安心感がある 業者の倒産リスクがない |
盗難・紛失のリスクがある 購入時に消費税がかかる 保管場所(貸金庫など)にコストがかかる |
| 純金積立 | 毎月少額(例:1,000円)から金を買い貯めていく | 少額から始められる 時間分散で価格変動リスクを抑えられる(ドルコスト平均法) |
手数料が比較的、割高になる傾向がある リアルタイムでの売買ができない |
| ETF(投資信託) | 証券口座で「株」のように金の権利を売買する | 売買が最も簡単(リアルタイム取引可) 保有コスト(信託報酬)が安い 購入時に消費税がかからない |
原則として、現物の金に交換できない 証券口座の開設が必要 |
このように、金への投資方法にはいくつかの選択肢があります。ご自身の状況に合わせ、最適な投資方法を選ぶことが大切です。
3.投資できる金現物の種類と特徴

金現物で投資対象となるのは、主に「インゴット(地金)」と「金貨(コイン)」の2種類です。それぞれの特徴について、解説していきます。
3-1.インゴット(地金):資産保全の王道
インゴット(地金)とは、国際的に認められた品質規格(主に純度99.99%以上)を満たした金の塊(のべ棒)を指します。
表面には、製造したブランド(業者名)、重さ、純度、製造番号が刻印されており、これが世界共通の信頼の証となります。重さは5g程度の小さいものから1kgの大きなものまでサイズが豊富です。
とくに金貨のようなデザイン料などが上乗せされないため、純粋な金の価値で取引できる「資産保全の王道」とされています。
3-1-1.インゴットのメリット
インゴットの利点は、金そのものの価値で取引されるシンプルな点です。
金貨とは異なり、デザイン料や製造コストといった付加価値が価格にほとんど含まれません。そのため、新聞やWebで公表される金価格のニュースを見ながら、売買の判断がしやすいのが魅力です。
また、500gや1kgといった「ラージバー」と呼ばれる大きなサイズで購入する場合、売買時の手数料(バーチャージ)がかからない(または割安になる)場合が多く、まとまった資金を金に換える際に最も効率的な方法といえます。
3-1-2.インゴットのデメリット
インゴットの欠点は、小さなサイズ(一般的に500g未満)を購入する場合に取引コストが高くつく点です。100gや20g、5gなどの小さい地金には、「バーチャージ」と呼ばれる別途手数料が購入時や売却時に発生します。
そもそもバーチャージとは、1kgの塊を小さく加工するための手間賃のようなものです。そのため、少額で売買を繰り返すのには向いていません。
また、実物なので盗難や紛失を防ぐための保管場所を確保する必要があり、その維持費もかかります。
3-2.金貨(コイン):少額から購入可能
金貨(コイン)投資は、各国の造幣局が発行するもので、投資用の「地金型金貨」が主な対象です。
金貨にはもう一つ「記念金貨」という種類がありますが、記念金貨はデザイン性や希少性で価格が決まる一方、地金型金貨は、金の市場価格にほぼ連動して価格が決まります。
インゴットが最低でも5g程度からの購入となるのに比べ、地金型金貨は1/10オンス(約3.1g)など、より小さな単位から購入できるのが特徴です。数万円程度の比較的少ない予算からでも金現物投資を始められることから、投資初心者にも人気があります。
3-2-1.代表的な金貨(メイプルリーフ金貨・ウィーン金貨)
世界的に流通している代表的な地金型金貨が、「メイプルリーフ金貨」と「ウィーン金貨」です。
「メイプルリーフ金貨」は、カナダ政府が品質を保証する純度99.99%以上(フォーナイン)の金貨で、表面にエリザベス女王(または国王)、裏面にカエデの葉がデザインされています。「ウィーン金貨」はオーストリア造幣局が発行し、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を象徴する楽器が描かれた美しい金貨です。
どちらも国際的な信頼性が非常に高い金貨として知られています。
3-2-2.金貨のメリット
金貨のメリットは、インゴットより少ない金額から購入できる手軽さと換金性の高さです。1オンス(約31.1g)のほか、1/2、1/4、1/10オンスなど小さなサイズが充実しています。これにより、予算に合わせて買い増しをおこなったり、必要な分だけを売却したりするのが容易です。
また、美しいデザインのものが多く、コレクションとしての楽しみもあります。希少な発行年やデザインの金貨には、金の価値以上の付加価値がつく場合があるのも魅力です。
3-2-3.金貨のデメリット
金貨のデメリットは、売買価格に「プレミアム(付加価値)」が含まれる点です。プレミアムとは、デザイン性や製造コスト、輸入コストなどが金価格に上乗せされたもので、同じ重さのインゴットに比べて割高になります。
また、インゴットと同様に実物資産であるため、自宅で保管する場合は盗難や火災のリスクに自分で備えなくてはなりません。
人気の金貨は偽造品が出回っている可能性もあるため、信頼できる業者から購入することが重要です。
4.金現物はどこで買える?
金現物は、主に以下の3箇所で購入することができます。
- 地金商
- 証券会社・銀行
- 宝石商・貴金属店
それぞれ解説します。
4-1.地金商(田中貴金属、三菱マテリアル、徳力本店など)
金現物の購入先として最も信頼性が高いのは、田中貴金属工業や三菱マテリアル、徳力本店といった専門の地金商です。これらの業者は、国際的な品質基準(ロンドン貴金属市場協会の基準)を満たしたインゴットを製造・販売しています。そのため、世界中どこでも価値が認められ、売却時もスムーズです。
地金商での金購入は、直営店や電話、インターネットを通じて、その日の金価格にもとづいた公正な取引がおこなえます。手数料体系も明確で、とくに500g以上の大きなインゴットを買う際は手数料が無料になる場合が多いです。
4-2.証券会社・銀行(三菱UFJ銀行、楽天証券など)
証券会社や銀行の一部でも、金の現物を購入できます。
たとえば楽天証券では、Webサイトを通じてインゴットの購入や売却が可能です。購入した金は自宅へ配送してもらうか、そのまま証券会社に預けて保管してもらうかを選べます。三菱UFJ銀行なども金の取り扱いをおこなっていますが、近年は現物の販売を縮小したり、純金積立のみに限定したりする金融機関が増えています。
普段利用している金融機関で手軽に買える利便性がありますが、取り扱いサービスの内容をよく確認するのが無難です。
4-3.宝石商・貴金属店(※購入手数料に注意)
金現物は、街にある宝石商や貴金属店でも購入が可能です。店舗で実物を見ながら相談できる手軽さが利点といえます。
ただし、購入時には注意が必要です。これらの店舗では、地金商や証券会社に比べて売買手数料が割高に設定されているケースが多く見られます。また、取り扱っているインゴットや金貨が、国際的な基準を満たしているか(たとえば有名な地金商の刻印があるか)を確認しなくてはなりません。
信頼できるお店かどうかを慎重に見極めることが大切です。
5.金現物購入の流れと手数料(コスト)

ここからは、金現物を購入する流れと手数料について、それぞれ解説していきます。
5-1.金現物を購入する流れ
金現物を購入する基本的な流れは、以下の3ステップです。
- 購入場所の選定と本人確認書類の準備
- 購入・支払い(※200万円超の取引はマイナンバー必須)
- 現物の受け取り
順を追って解説していきます。
5-1-1.①購入場所の選定と本人確認書類の準備
金現物を購入するときは、まずどこで購入するのかを決め、本人確認書類を準備してください。
金現物の購入先には、信頼性の高い地金商、手軽な証券会社、身近な貴金属店などがあります。それぞれのメリットや手数料を比較して、自分に合った場所を選びましょう。
また金現物の購入時には、「犯罪収益移転防止法」という法律にもとづき、本人確認が必ずおこなわれます。そのため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(住所記載のあるもの)など、顔写真付きの身分証明書をあらかじめ用意しておきましょう。
5-1-2.②購入・支払い(※200万円超の取引はマイナンバー必須)
購入先を決めたら、当日の金価格を確認して購入の申し込みをおこないます。店頭の場合は申込書に記入し、インターネットの場合は画面の指示に従って手続きを進めます。支払いは現金持参のほか、銀行振込が一般的です。
ここでとくに注意すべき点は、1回の取引額が200万円を超える場合です。この場合、本人確認書類に加えて、マイナンバー(個人番号)の提示が法律で義務付けられています。これは、業者が税務署に「誰がいくらの金取引をしたか」を報告する「支払調書」を作成するためです。
定められたルールに則り、金を購入しましょう。
5-1-3.③現物の受け取り
代金の支払いが完了したら、最後に金現物を受け取ります。受け取り方法は、主に「店頭受け取り」と「配送」の2種類です。
地金商の直営店などで購入した場合、その場で現物を受け取り、重さや刻印などを確認できます。証券会社やインターネット販売を利用した場合は、保険がかけられた配送便で自宅に送られてきます。
また、金現物の盗難や紛失が心配な場合は、配送を選ばず、購入先の会社が提携する倉庫などでそのまま預かってもらう「保護預かり」サービスを利用するのも一つの方法です。
参考:わかりやすい用語集 解説:保護預かり(ほごあずかり) | 三井住友DSアセットマネジメント
5-2.金の現物購入時に注意すべき点
金の現物購入時に注意すべき点は、以下の2点です。
- スプレッド(売買価格差)がかかる
- バーチャージ(500g未満の手数料)がかかる
それぞれ解説します。
5-2-1.スプレッド(売買価格差)がかかる
金現物の取引では、「スプレッド」と呼ばれる実質的なコストがかかります。スプレッドとは、販売店が提示する「購入価格(金を購入する値段)」と「売却価格(金を売却する値段)」の差額のことです。
基本的に金の販売業社は金を安く買い取り、高く売ることで利益を得ています。そのため、購入価格は常に売却価格よりも高く設定されているのです。
この価格差があるため、金を購入した瞬間に売却しようとすると、スプレッドの分だけ必ず損をします。金投資で利益を出すには、このスプレッド以上に金価格が上昇するのを待つ必要があります。
5-2-2.バーチャージ(500g未満の手数料)がかかる
バーチャージとは、500g未満の小さなインゴットを購入または売却する際に発生する手数料です。
金地金は、1kgの大きな塊(ラージバー)を基準に取引されるのが基本です。100gや20gといった小さなサイズにするには、金を溶かして分けたり、刻印を押したりする加工の手間(コスト)がかかります。そのコストを補うための手数料がバーチャージです。
一般的に500gや1kgのインゴットの売買ではバーチャージはかかりませんが、それより小さいサイズは割高になるのを覚えておく必要があります。
6.購入した金現物の保管方法
購入した金現物の保管には、主に以下3つの方法があります。
- 自宅保管
- 銀行の貸金庫
- 地金商などの保管サービス
詳しく見ていきましょう。
6-1.自宅保管(家庭用金庫)
自宅保管は、購入した金現物を自分の家で管理する方法です。
自宅保管最大のメリットは、銀行や専門業者に支払う保管料が一切かからず、コストを抑えられる点です。また、金融機関の営業時間に関係なく、いつでも好きなときに金を取り出したり、売却の判断をしたりできる自由度の高さも魅力といえます。
ただし、盗難や火災、地震などの災害によって金を失うリスクをすべて自分で負わなくてはなりません。そのため、耐火性や防盗性に優れた家庭用金庫を用意するなど、厳重な防犯・防災対策が不可欠です。
6-2.銀行の貸金庫
銀行の貸金庫は、銀行内の厳重なセキュリティで守られた金庫室の一区画を借りて、金現物を保管する方法です。専門の施設であるため、盗難や火災、災害に対する安全性が非常に高いのが最大のメリットです。
ただし、利用するには月額または年額で数千円から数万円の利用料がかかります。また、原則として銀行の営業時間内でしか金の出し入れができません。急に金が必要になった場合でも、夜間や休日には対応できないのがデメリットといえるでしょう。
6-3.地金商などの「特定保管」サービス
地金商などが提供する「特定保管」サービスは、購入した金をそのまま専門業者の金庫で預かってもらう方法です。銀行の貸金庫と似ていますが、これは「金を預ける」専門のサービスを指します。
特定保管では、預けた金の所有権は預け主のままで、業者の資産とは明確に分けて管理されます。万が一業者が倒産した場合でも、預けた金は守られるのが大きな特徴です。
セキュリティが高い環境で保管料も比較的安価な場合がありますが、出し入れに手続きが必要になります。
7.金現物投資にかかる税金
金現物投資には、「購入時」「売却時(利益が出た場合)」「相続時」の3つのタイミングで税金がかかります。金現物の取引で最終的に手元に残る利益を考えるうえで重要な要素となるため、十分に理解しておきましょう。
それぞれ解説します。
7-1.購入時:消費税がかかる
現行の消費税法に則り、金現物を日本国内で購入する際には、購入代金に対して10%の消費税がかかります。たとえば、金の本体価格が100万円だった場合、消費税10万円を加えた合計110万円を支払う必要があります。これは、金が法律上「モノ」として扱われるため、食料品や家電を買うのと同じです。
一方、金を売却する際は、売却代金に消費税分が上乗せされて戻ってくる形になります。ただし、個人が趣味などで金を売却した場合、受け取った消費税を国に納める義務(納税義務)は原則としてありません。
7-2.売却時(利益が出た場合):譲渡所得として課税される
金現物を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税の課税対象となります。譲渡所得には年間50万円の特別控除(非課税枠)があるため、年間の利益が50万円以下であれば税金はかかりません。
また、金の保有期間が5年を超えていると「長期譲渡所得」となり、利益をさらに半分にしてから税額が計算されます。そのため、金投資は5年以上の長期保有が税金面で有利です。
なお、営利目的で金の売買を繰り返していると、事業所得や雑所得とみなされる場合があります。
7-3.相続時:相続税の対象となる
保有している金現物は、預貯金や不動産と同じように「相続財産」の一部とみなされ、相続税の課税対象となります。
金の相続税評価額は、亡くなった日(相続開始日)の「業者買取価格(小売価格ではない)」にもとづいて計算されます。たとえば、相続開始日の1gあたりの買取価格が10,000円で、1kgのインゴットを保有していた場合、その金の評価額は10,000,000円として相続財産に加算されます。
金のまま保有していても相続税の対象となるため、注意が必要です。
8.まとめ
この記事では、金現物投資のメリット・デメリットから、インゴットと金貨の違い、具体的な購入場所や手順、そして最も重要な保管方法と税金について詳しく解説しました。
金現物投資は、「実物」を手元に置ける絶対的な安心感が最大の魅力ですが、盗難リスクや保管コスト、購入時の手数料といったデメリットも存在します。ご自身の投資目的が手軽さやコストの安さであればETFや純金積立といったその他の投資方法が適しているかもしれません。
この記事を参考に、ご自身の資産状況や目的に最適な金の持ち方を選び、将来への確かな備えを始めてみてはいかがでしょうか。
玉光堂では、以下の2つの方法で金の買取を実施中です。金・貴金属の売却を検討している方は、ぜひ玉光堂の金買取をご利用ください。
玉光堂の選べる買取方法