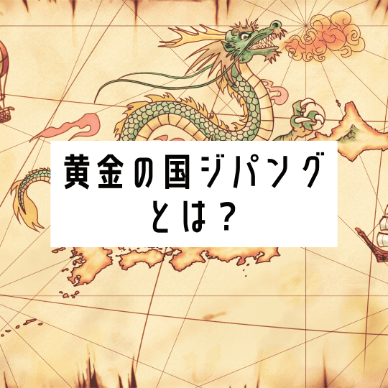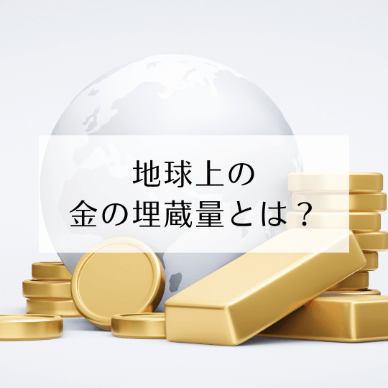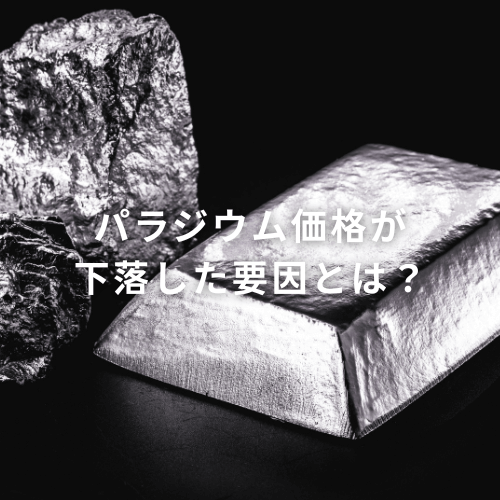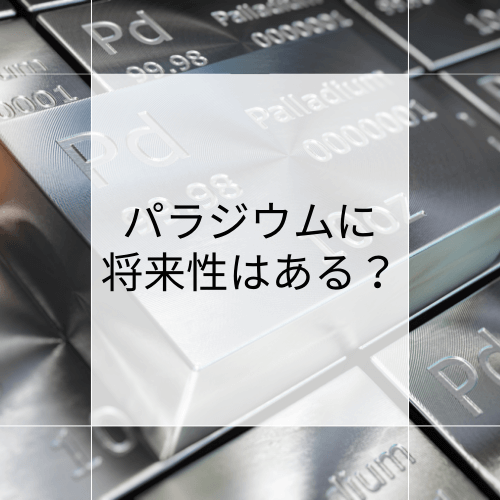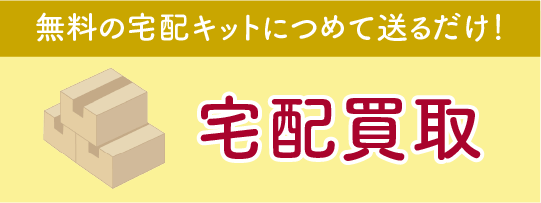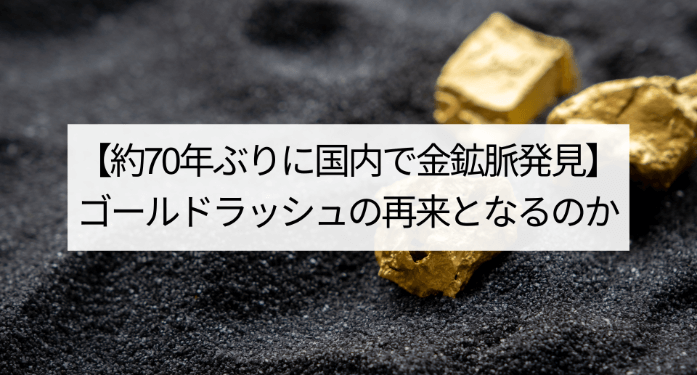
2025年に入り、日本国内のとある金山から金鉱脈が発見されたというニュースが流れました。そのニュースに驚いたという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、約70年ぶりとなる金鉱脈発見について、その概要から今後の展望まで詳しく解説していきます。
金鉱脈の発見について概要を知りたいという方や、今後について知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
金相場1g円の過去最高水準!
今が売り時です!
他店に負けない金の高価買取を実施中
金の買取なら、「玉光堂」の高価買取の「玉光堂」まで。
【目次】
1.約70年ぶりに日本国内で金鉱脈が発見された

日本国内にて、約70年ぶりに金鉱脈が発見されました。実際に、以下のようなニュースでも取り上げられています。
参考:70年ぶり日本で金鉱脈発見 期待はゴールドラッシュの再来 周辺では砂金も 鹿児島|テレ朝NEWS
日本はかつて「黄金の国ジパング」と呼ばれたほど、金が豊富に採れる国でした。しかし、コストの問題で多くの鉱山が閉山し、長らく大規模な新規開発はおこなわれてきませんでした。
ところが近年、金の価格高騰や探査技術の進化を背景に、海外企業や国内大手が再び調査に乗り出しています。その結果、過去の大規模鉱山に匹敵するような、質の高い金鉱脈の存在が明らかになりつつあるのです。
1-1.今回発見された金鉱脈の所在地
今回注目されている金鉱脈がある山ケ野金山(やまがのきんざん)は、鹿児島県霧島市横川町に位置します。
山ケ野金山は、江戸時代から昭和初期まで金の採掘がおこなわれていた歴史ある金山です。1950年代前半に閉山しましたが、坑道跡や選鉱場跡などの遺構が残り、かつての鉱山としての面影を今に伝えています。
そして約70年前に閉山した山ケ野金山から今回金鉱脈が発見され、再び注目を集めることとなりました。
1-2.金鉱脈発見の経緯
山ケ野金山にて金鉱脈発見の経緯は、最新の探査技術の導入と、世界的な金価格の上昇が主な要因です。以前の技術では発見が難しかった地下深くの微細な反応も、衛星データや高度な物理探査を用いることで、高精度に特定できるようになりました。
今回の調査を主導したのは、カナダの探鉱会社アービング・リソース社と米国の産金会社ニューモント社、住友商事でつくる特定建設工事共同企業体です。
参考:72年前に閉山、山ケ野金山から新たな金鉱脈見つかる――金含有量は「優良」基準超え、さらに精密な調査計画 霧島市横川 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル
世界的に金価格が高騰するなか、かつては採算が見込めなかった旧鉱山でも、再び事業化のチャンスがあるとして、山ケ野金山周辺のボーリング調査が積極的に進められました。
さらに、金価格が歴史的な高値圏で推移しているため、採掘コストをかけても十分に利益が出ると判断されたのが、再開発の大きな後押しとなっています。
1-3.ボーリング調査による調査結果
ボーリング調査による調査結果では、世界平均を大きく上回る「1トンあたり9.62g(一部区間では1トンあたり45.9g)」という高品位な金の含有量が確認されています。
通常、金鉱山では鉱石1トンあたり3gから5g程度の金が含まれていれば採算が取れるといわれています。その数値と比較すると、今回の「1トンあたり9.62g」という数値は世界中の鉱山関係者が驚くレベルです。日本列島の地下には、依然として世界トップクラスの質を持つ金脈が隠されているのが証明されたといえるでしょう。
2.そもそも金鉱脈とは?
そもそも金鉱脈とは、地下の岩盤の割れ目に金を含んだ熱水が入り込み、冷え固まってできた鉱石の層のことです。
地球の深部にあるマグマは、金などの金属成分を溶かし込んだ高温の熱水を持っています。この熱水が地殻変動でできた岩の隙間を通って上昇し、地表近くで急激に冷やされると、溶け込んでいた金が結晶となって沈殿します。
つまり、金鉱脈は火山活動と密接に関係しており、火山大国である日本は、金鉱脈ができるための理想的な環境が整っている場所なのです。
2-1.金鉱脈の定義
金鉱脈の定義は、経済的に採掘する価値があるほど金が濃集している「鉱床(こうしょう)」の一種です。
単に土や岩に微量の金が含まれているだけでは、金鉱脈とは呼びません。採掘コストを上回るだけの量がまとまって存在しているのが条件となります。
たとえば、川底で砂金が見つかることがありますが、あれはもとに山にあった金鉱脈が風化して川に流出したものです。したがって、砂金が採れる川の上流には、その発生源となる金鉱脈が存在している可能性が高いといえます。
2-2.金鉱脈の種類
金鉱脈の種類として、熱水鉱床と砂金鉱床の2種類が一般的です。
熱水鉱床は、地下深くのマグマの熱や地熱によって温められた熱水が、地殻の割れ目や隙間を通って上昇・循環する過程で、地中の金属成分を溶かし込み、その熱水が冷えたり、化学反応を起こしたりすることで、金属が沈殿・濃縮して形成される鉱床です。
一方砂金鉱床は、既存の鉱床が風化・侵食によって破壊され、そこに含まれていた金が水流によって運搬・堆積して形成される鉱床です。特に比重の重い金(砂金)が、川底の特定の場所や海岸に溜まることでできます。熱水鉱床のような地質的な化学作用ではなく、物理的な作用(水流と重力)によって形成されるのが特徴です。
そして山ケ野金山の金鉱脈は、前者の熱水鉱床に該当します。
2-3.金鉱脈を発見する方法
金鉱脈は、広大なエリアから有望な場所を絞り込み、最終的にピンポイントで掘削されることで発見されます。
ここでは、具体的な調査のステップや、金鉱脈ができやすい条件について詳しく解説します。
2-3-1.金鉱脈の調査方法
金鉱脈の調査方法は、まず衛星写真や地質図をもとに有望なエリアを選定し、現地で岩石を採取する「地表地質調査」から始まります。
地表での調査で金の兆候が見つかると、次は「物理探査」をおこないます。電気を流して地下の抵抗を測ったり、重力のわずかな変化を調べたりと、地下構造を推定するのです。
最終的には、実際に機械で穴を掘る「ボーリング調査」をおこない、地下から取り出した岩石サンプルを分析して、どれくらいの金が含まれているかを確定させます。
2-3-2.金鉱脈ができる場所の条件
金鉱脈ができる場所の条件は、過去または現在において火山活動が活発であり、なおかつ地下に熱水の通り道となる「断層(岩盤の割れ目)」があることです。
金はマグマ由来の熱水によって運ばれるため、火山の近くであることが第一条件です。さらに、熱水が上昇するための隙間がなければ、金は地表近くまで上がってきません。
日本はプレートの境界に位置しており、火山帯と断層が重なり合う場所が数多く存在します。そのため、日本国内の至る所に金鉱脈が眠っている可能性が秘められているのです。
2-3-3.今後期待されている金鉱脈は「海底」
現在、金の採掘への期待は、陸上から日本近海の「海底」へと移っています。日本の排他的経済水域(EEZ)の海底には、「海底熱水鉱床」と呼ばれる、新たなゴールドラッシュの可能性が眠っているからです。
海底では、熱水の噴出孔が形成する「チムニー」と呼ばれる煙突状の構造物周辺で、金や銀、銅、さらにはレアメタルを含む鉱床が現在進行形で生成されています。
特に、沖縄近海や伊豆・小笠原諸島周辺では有望な鉱床が多数発見されており、将来的にはこの海底資源の開発によって、Webやニュースで「海洋からのゴールドラッシュ」が大きな話題となる日も遠くないかもしれません。
3.日本の歴史における代表的な金鉱脈
日本では、これまでに多くの鉱山にて金鉱脈が発見されています。北は北海道から南は九州まで、日本列島には火山活動によって形成された金脈が数多く存在しています。
歴史の教科書に登場するような有名な金山から、現在も稼働している世界有数の高品位な鉱山まで、日本の金を語るうえで欠かせない5つの代表的な金鉱脈について解説します。
- 佐渡金山
- 鴻之舞鉱山
- 玉山金山
- 鯛生金山
- 菱刈鉱山
一つずつ見ていきましょう。
3-1.佐渡金山
佐渡金山は、約400年にわたり採掘が続けられた、日本最大級の金銀山です。新潟県の佐渡島に位置し、江戸時代には徳川幕府の財政を支える重要な資金源として栄えました。
手掘りでおこなわれた坑道や、山がV字に割れた「道遊の割戸」などの遺構は、当時の採掘技術の高さを示す貴重な史跡となっています。2024年にはユネスコの世界文化遺産に登録されるなど、歴史的価値が世界的に再評価されている場所でもあります。
3-2.鴻之舞鉱山
鴻之舞(こうのまい)鉱山は、かつて「東洋一の金山」とうたわれた北海道紋別市にあった鉱山です。1915年の発見から1973年の閉山までの間に、金73トン、銀1234トンという莫大な産出量を記録しました。
最盛期には1万人以上の人々が暮らす鉱山街が形成され、日本の近代化と経済発展に大きく貢献した場所です。現在は閉山していますが、巨大な煙突や発電所の跡地などが産業遺産として残っており、当時の繁栄を今に伝えています。
3-3.玉山金山
玉山(たまやま)金山は、岩手県陸前高田市に位置し、「黄金の国ジパング」伝説のモデルになったともいわれる歴史ある金山です。その歴史は非常に古く、奈良時代に高僧・行基によって発見されたという伝説があります。
一攫千金を夢見た多くの人々が集まり、水晶のなかに金が含まれた「金入水晶」なども産出されました。千年以上もの間、日本の黄金文化を支え続けた伝説的な場所といえるでしょう。
3-4.鯛生金山
鯛生(たいお)金山は、明治から昭和にかけて栄え、佐渡金山を抜いて日本一の産出量を誇った時期もある大分県の金山です。1938年の最盛期には年間2.3トンもの金を産出し、東洋の黄金郷として名を馳せました。
地下深くには総延長110キロメートルにも及ぶ坑道が張り巡らされており、閉山後の現在は地底博物館として整備されています。当時の採掘現場をリアルに体験できる観光スポットとして、多くの人々が訪れる場所となっています。
3-5.菱刈鉱山
菱刈(ひしかり)鉱山は、現在も商業的な採掘がおこなわれている国内最大の現役金山です。鹿児島県伊佐市に位置し、1981年の発見以来、現在までに約260トン以上の金を産出しています。
特筆すべきは鉱石の品質で、世界の主要金山の平均が鉱石1トンあたり3〜5gの金含有量であるのに対し、菱刈鉱山は約20gから40gという驚異的な高品位を誇ります。まさに世界トップクラスの「奇跡の鉱山」です。
4.今回新しく発見された山ケ野金山の金鉱脈の今後について

今回新しく発見された山ケ野金山の金鉱脈の今後は、本格的な商業化に向けた詳細な調査と、地域経済への貢献が期待されています。
ここでは、この新鉱脈が持つポテンシャルと、今後の社会への影響について詳しく解説します。
4-1.鉱脈内に眠る金の含有量が鍵
山ケ野金山は、現時点では本格採掘が決定したわけではありません。今後の調査によって、採掘の方向性が定められていきます。
今後の開発において最も重要な鍵となるのが、鉱脈内に眠る金の含有量です。採掘にかかる莫大なコストを回収し、利益を生み出すためには、鉱石1トンあたりに含まれる金の量が非常に重要になります。
現在調査がおこなわれているのは、ごく一部のサンプルです。これがどれくらいの広がりを持つのか、埋蔵量が十分かどうかが鍵となります。
十分な含有量が認められ「質」の高さが確定すれば、長期にわたり安定して金を供給できる重要な拠点となるでしょう。
4-2.山ケ野金山の金鉱脈が経済に与える影響
山ケ野金山の新鉱脈開発は、金の安定供給だけでなく、地元鹿児島県の経済活性化にも大きな影響を与えます。
本格的な鉱山開発が始まれば、現地での雇用創出やインフラ整備が進み、地域全体にお金が回るようになるからです。また、金価格が高騰を続けるなか、国内で採掘できる資源が増えるのが、日本の資源セキュリティの向上にも直結します。
「令和のゴールドラッシュ」として、地方創生の大きな起爆剤になることが期待されています。
5.まとめ
この記事では、約70年ぶりに日本国内で発見された、山ケ野金山の高品位な金鉱脈について詳細を解説しました。世界平均を大きく上回る金の含有量は、「黄金の国ジパング」のポテンシャルが日本列島の地下に今なお眠っていることを証明しています。
金鉱脈の形成原理(熱水鉱床)や、佐渡金山・菱刈鉱山といった歴史的な鉱脈の解説を通じて、金が火山活動と密接に関わる日本の「地下資源」であることをご理解いただけたでしょう。
今後は、この山ケ野金山の本格開発に加え、海底熱水鉱床という新たなフロンティアにも期待が寄せられます。「令和のゴールドラッシュ」が、国内の資源セキュリティ向上と地域経済の起爆剤となることを期待しましょう。
玉光堂では、以下の2つの方法で金の買取を実施中です。金・貴金属の売却を検討している方は、ぜひ玉光堂の金買取をご利用ください。
玉光堂の選べる買取方法